アクサ流「お金の教養」
キャッシュレス時代に身に付けたいお金と向き合うリテラシー
Vol.8 「金を使う」という習慣との付き合い方
キャッシュレス時代に身に付けたいお金と向き合うリテラシー
Vol.8 「金を使う」という習慣との付き合い方
今後、ますます増加することが予想される「キャッシュレス決済」。しかし、便利さの裏側で「目に見えない、手で触れないお金だからこそ、きちんと管理をしないと、気付いたときには自分の大切な資産を損なうことになりかねない」「金銭感覚がおかしくなりそう」といった心配の声も聞かれます。
前回は、キャッシュレス決済が引き起こす可能性のある、「使い過ぎ」や「依存」のメカニズムについて考えてみました。
今回は、キャッシュレス時代是非身に付けておきたい、「使いすぎ」や「依存」に対する、「予防」のテクニックについて、引き続き大船榎本クリニック(神奈川県・鎌倉市)精神保健福祉部長、精神保健福祉士・社会福祉士の斉藤章佳さんにお話を聞きました。
依存状態にならないためには「依存先を増やすこと」が大事


――誰もがもっている「認知の歪み」が、過度な依存につながる場合と、そうでない場合とでは、どんな違いがあるのでしょうか?
『人間は習慣化している行動、特に、報酬系を刺激する行動は脳内の神経伝達物質であるドーパミンを過剰分泌させるため、その行動をさらに繰り返す傾向があります。そして、反復していくうちに、条件反射の回路が脳内に構築されます。嗜癖(しへき)行動は、この「条件反射の回路」と結びついています。
買い物も生活習慣のひとつですよね。買い物に耽溺している状態のひとは、その習慣を繰り返すうちに、「買いたい!そして、快の感情を味わいたい」という条件反射のスイッチが入るようになってしまうと言えるでしょう。
ただ、衝動が起きて、破綻するような買い物に走ってしまう要因を見ていくと、その背景には、過度なストレスや人間関係のトラブル、過去の逆境体験があったりします。このような問題行動が再発する要因となるきっかけを「引き金�(トリガー)」と言います。
ですから、嗜癖状態から抜け出すには、まずそのひとにとってのハイリスクな状況を特定し、トリガーを明確にする必要があります。それができたら、ハイリスクな状況になったときにどう対処するか、また悪循環のサイクルはどのように始まるのかを理解したうえで、あらかじめ対処法を決めておくのです。この対処行動を「コーピング」と呼びます。』
――具体的にコーピングにはどのようなものがあるのでしょうか?
『実は、私は昔、どう考えてもからだに良くないのに、夜寝る前にスナック菓子を食べるのがやめられない時期がありました。その“スナック菓子依存症”に対処するためのコーピングは、私にとっては、早く寝るとか、炭酸水を飲むとか、歯を磨くことでした。
ひとによってコーピングはさまざまあるのですが、残念ながら、慣れてくるとだんだん効かなくなっていくものでもあります。これを「コーピングの耐性」と呼んでいます。ですから、「これで対処する!」と決めつけてこだわらないようにすることが大切です。より簡単に言うと、ストレス対処法の選択肢を複数用意しておくことが大事だ、ということです。
少し妙な言い方に聞こえるかもしれませんが、「依存状態にならないよう、依存先を増やすことが重要」というわけです。』
――「強い意思で頑張ってガマンする」というものではない、ということですね。
『依存状態に陥ることは、「意思が弱いから」と言われることも多いですが、誰でも挫折することはありますし、大切なひとを失ったとき、家庭や仕事がうまくいかないときもあるので、それがト�リガーとなって不適切な習慣に耽溺することは、どんなひとでも起きえます。
ただ、どんな種類の依存症でも、症状が進行するひとに共通しているのは、大切なひととの人間関係を失い、どんどん孤立していく傾向が強くある、ということです。
誰にも相談できず、ひとりで抱え込んでしまい、唯一の“依存先”になってしまったアルコールや買い物、薬物などにより深くハマっていく、という負の連鎖になっているわけです。
そうではなく、細くてもたくさんの対処法や相談相手、くつろげる場所などの“つながり”を持っている方が、ついつい無駄遣いしてしまったり、食べ過ぎや飲み過ぎといった、そのひとにとっての“危機的な場面”に直面したときにも対処がしやすくなります。』
可視化し、共有することが予防の鍵になる
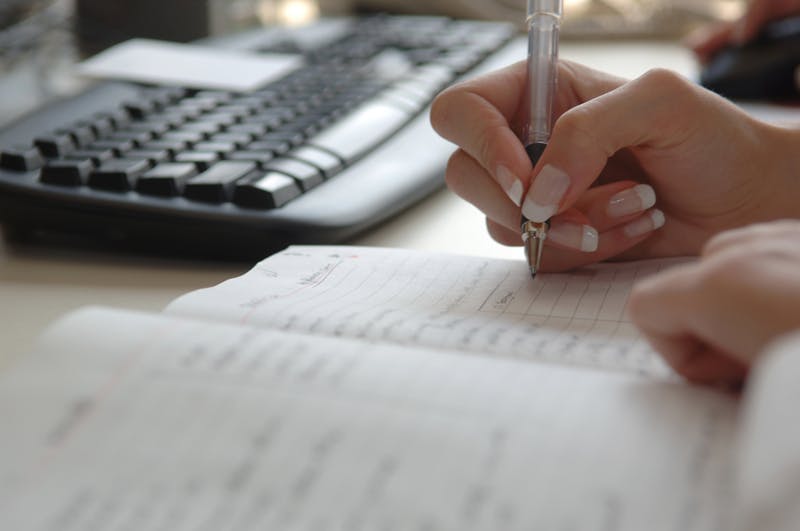
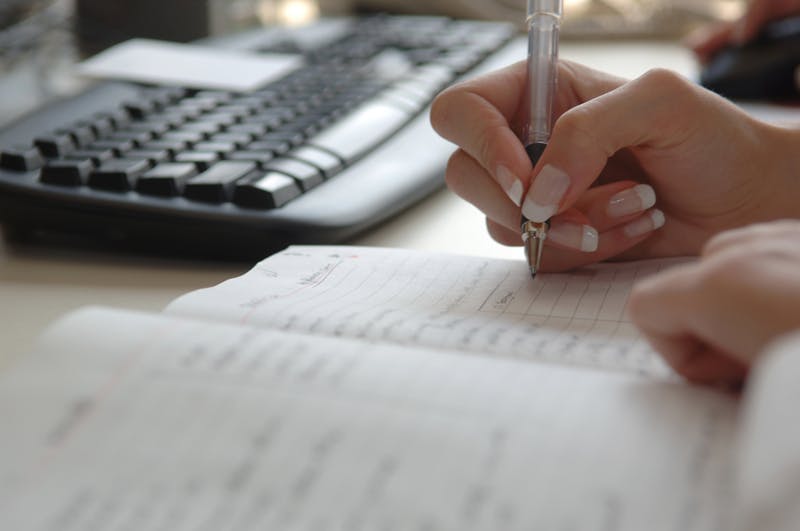
――依存するとまではいか��なくとも、たびたび使いすぎてしまうことがあったり、キャッシュレスとの付き合い方に不安があるひとのために、「予防」のテクニックがあれば教えてください。
『まずは自分で具体的なルール設定をしておくことでしょうか。私の“買いすぎ対策”を一例としてご紹介すると、ネットでワンクリックで本を買いすぎてしまわないように、「一冊読み終えたら次の本を買う」ことと「なるべく本屋さんで買い、ネットで購入しない」というルールを設定しています。そうしないと、パソコンやスマホの画面上に出てくるおもしろそうな本を無制限に買ってしまって「積ん読」ばかりが増えてしまうからです。
同じように、「買いすぎてしまう」と思うなら、現金で購入する場合とクレジットカードで購入する場合の条件を具体的に決めたり、カードの上限額をきちんと設定しておくといいでしょう。
このほか「レコーディング」つまり、記録することは有効な手段として挙げられます。これはプレアルコホリック(予備軍)の依存症の予防法としてエビデンスがあります。
少し話が脇道にそれますが、一度アルコール依存症になってから「断酒」しようと思うと、非常にハードルが高くなります。そこで、最近では、依存症になる前の「予備軍」の段階で、それ以上進行させないように「減酒」を促す治療法が行なわれるようになっているんです。
そのときにやってもらうのが、日々の飲酒量のレコーディング(記録)です。1日の適正飲酒量のアルコールグラム数があるので、それと照らし合せていくと、自分の状況を可視化して客観的に判断しやすくなるますし、どういうタイミングで飲みすぎてしまうかなどの傾向も見えてきます。
キャッシュレス決済の場合は、クレジットカード会社からの明細や、電子マネーのアプリの使用履歴などで記録が残り、振り返りやすいと言えます。それをきちんと毎月チェックして、これまでのお金のつかい方と比較しながら、自分が使いすぎてしまう傾向を分析してみるといいでしょう。
もし細かい数値を見たりレコーディングするのが苦手なら、使いすぎてしまった日に赤いシール、使いすぎてしまいそうだった日に黄色シール、問題がなかった日に青いシールを、それぞれカレンダーに貼っていくのも、自分の状況を一覧化できるのでおすすめです。』
――自分ひとりでそれをやっていると、ズルやごまかしをしてしまう、なんてことはありませんか?
『確かに、ひとりだけでやっていると、続かなかったり、誤魔化したりしやすいですよね。しかし、依存症治療の経験からお話しすると、こうした記録を誰かと一緒に取り組むと、継続率が圧倒的に高くなりますし、嘘をつき続けるのがつらくなるから正直に申告するようになります。また、「仲間も頑張っているから自分も」と、望ましい行動を継続しようと努力するようにもなり、非常に効果的です。
できれば当事者同士、例えば「クレジットカードをどうしても使いすぎてしまうひと同士」や「少額決済で無駄なものを買いすぎてしまうひと同士」が集まってみんなで問題を解決するような取り組むのが一番です。それぞれの失敗体験が、他の仲間の力になります。
しかし、問題意識を共有できれば、同じ問題を抱えていなくても構いません。家族やファ��イナンシャルプランナーに伴走してもらうのもいいと思いますね。ただ、ここでのポイントは「同じ悩みに向き合っていく」ことであって、誰かがコーチになって導くような上下関係を築くわけではない、ということです。』
*****************
人生100年時代において、今後も「お金」の“カタチ”は変化していくかもしれません。それぞれの特徴や懸念点も存在するはずですが、その“カタチ”の違いによらず、「お金」の健康的な管理と、心と体の健康管理は結びついていると言えそうです。その両論を、自分自身だけでなく、ときには周囲を頼りながら、メンテナンスし続けてみませんか?
斉藤 章佳(さいとう・あきよし)
大船榎本クリニック(神奈川県・鎌倉市)精神保健福祉部長、精神保健福祉士・社会福祉士。大学��卒業後、アジア最大規模といわれる依存症施設「榎本クリニック」に約20年間ソーシャルワーカーとして、アルコール依存症を中心にギャンブル・薬物・摂食障害・性犯罪・児童虐待・DV・クレプトマニアなどさまざまアディクション問題に携わる。話題の本『男が痴漢になる理由』(イースト・プレス)、『小児性愛という病ーそれは、愛ではない』(ブックマン社)をはじめ最新刊『しくじらない飲み方ー酒に逃げずに生きるには』(集英社)など、著書多数。
AXA-A2-2008-0423/844