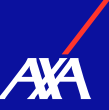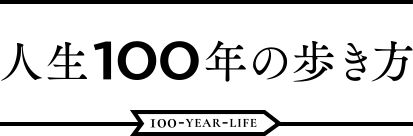都築電気の「健康経営と福利厚生」を知ることで得た学生の気づきとは!?~成城大学経済学部生が学んだ、企業を「健康経営」の視点から見ていくポイント~
2025年08月15日 | 会社経営のこと -Business-

成城大学経済学部の「経営学特殊講義A(柴田喜幸先生)」では、「健康経営」をキーワードに、「各企業が大切にしているものを見極める眼を養い、自分の価値にあった企業選択やその後のキャリア開発の力をつける」を掲げた授業が行われています。これに協力しているのがアクサ生命です

産業医科大学 産業医実務研修センター 副センター長 柴田 喜幸先生
この授業では、毎回、企業・行政・コンサルタントなど多彩なゲスト講師を迎えます。ゲストの取組みや社会動向を聞き、それを受けクラス内で話しあい、「自分の価値」と照らし合わせ、企業や社会を見る視点を育んでいきます。
そこに共通して流れているのが「健康経営的思想」です
今回第10回には、情報通信業の大手で、東証プライム市場にも上場している都築電気株式会社から、人事部担当課長の奥野洋子さんを特別講師としてお迎えしました。
「健康経営」がもたらすポジティブな影響がリアルに伝わりました。同社がどんなふうに「健康経営」に取り組んでいるのか、奥野さんご自身の経験を交えてご紹介いただきました。企業選びの視点として「健康経営」をどう見ればいいのか、学生たちが気になるポイントをわかりやすく解説してくれましたので、その内容をお届けします。
企業における健康経営の取り組み方とは?
定刻になりチャイムが鳴ると授業が開始されます。教室内には夕方の講義にも関わらず、熱心な学生が20名以上集まっています。その多くは3年生ということで、これから就職活動を迎える学生が多くいるようです。そんな学生たちが、今日の奥野さんの講義からどのようなことを学び、どのような反応を示してくれる��か楽しみです。

都築電気株式会社 人事部 担当課長 奥野 洋子さん
講義の最初は奥野さんの自己紹介から始まる…と思いきや、奥野さんは突然「皆さん、立って肩を回しましょう!」と提案。この講義は金曜日の夕方ということもあり疲労が溜まっていると感じたのか、そして何よりも「健康経営」というテーマであることもあり、まずは健康的に身体を動かして、話す側も聞く側の集中力を高めてから講義に入りたいという意図があったようです。
ひと通り身体をほぐして、教室全体に活気と笑顔が広がったところで、改めて講義がスタートです。奥野さんが所属する都築電気は創業93年。情報通信の世界で長い歴史を持つ同社で人事部に所属する奥野さんは、「過労死のない世界を作り、誰もが一生涯幸福を追求できる社会を作ること」を自身の人生におけるパーパスとして掲げていることを紹介してくれました。
奥野さんは学生時代、介護のボランティア活動に取り組んでいました。法改正により現場の働き方が大きく変化した経験から、大学を編入して“法律を作る側”を目指して勉強を始めたとのこと。学びを深める中で「もっと社会に出て、“事”を作る人になりたい」と考えるようになったそうです。というのも、物事の流れを��よくよく見てみると、「事が起こってから法律が作られる」ことに気づいたから。じゃあ、その“事”を最初に作っているのは誰か?と考えたときに、「それって民間企業じゃない?」という答えにたどり着いたそうです。
そんな思いから、奥野さんは現在の都築電気に就職。企業の中から社会を動かす“事”を作っていく道を選んだ、という経緯を語ってくれました。
そんな都築電気に入社後は、営業から新規事業企画、経営企画、広報を経て、現在は人事部で活躍されていますが、その中でも一貫して「働き方改革や健康経営に携わってきた」とのことで、この後の講義にも期待が膨らみます。
今日の講義のテーマは「健康経営と福利厚生から見る企業~都築電気の場合~」です。健康経営も福利厚生も、社会人経験のない学生からするとイメージしづらい部分があるかもしれませんが、数年後には社会へ出ることを考えると、このタイミングでこのような講義を受けるのは非常に幸運なのではないかと思います。

さて、最初のパートでは「かつて“働き方に課題があった”都築電気が、どうやって“働きやすい会社”へと変わっていったのか」という、ちょっと気になるテーマを取り上げます。
所属する組織の環境を、より良い方向へと本気で変えていくのは、簡単なことではありません。でも奥�野さんは、実際にその変化を実現してきた方。だからこそ、「都築電気は今、ホワイト企業だ」と胸を張って言えるのは、これまで積み重ねてきた努力がしっかりと形になっている証なのではないでしょうか。
最初のスライドでは、都築電気の株価の推移が示されました。2017年から健康経営を実践し始めると、なんと株価も業績も右肩上がりで上昇するようになったとのこと。働き方改革をおこなったことで、労働時間は短くなり、休暇も以前より取得できるようになったにも関わらず、業績は伸びているという、非常に理想的な状況を作り出しています。
ここで奥野さんから学生に「サステナビリティ(持続可能性)という言葉を聞いたことありますか?」と質問が飛びます。しかし、学生にはあまり馴染みのない言葉かもしれません。奥野さんは、「今の時代、企業は自分たちの利益だけを追い求めるのではなく、社会全体の持続可能性を意識しながら、自分たちの事業をどう活かしていくかを考えることが大切です」と語ります。
都築電気は「人と知と技術で、可能性に満ちた“余白”を、ともに。」というパーパスを掲げています。企業活動を通して、社会や人々が未来を描くための“余白”を生み出す、という考えを持っているとのこと。
パーパスを体現する重要なテーマとして5つの「マテリアリティ」を定め、健康経営は「『人』の成長と活性化」というマテリアリティのなかで取り組みを進めています。全社的に健康経営を推進しつづけた結果、都築電気は経済産業省が認定する「健康優良法人(大規模法人部門)」に8年連続で認定されるなど、健康経営について着実な実績を築い�ていることが紹介されました。
さて、そんな講義を聞いていると、ふと原点に立ち返って「健康経営」とは何だろう?と疑問が湧く学生もいるはずです。この解決しておかなくてはいけない問に対し、奥野さんは「健康経営とは従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践すること。そして単なる心身の健康だけでなく社会的にも健康である状態」という定義を答えとして用意してくれていました。
企業の視点では、社員が休む間もなく長時間働き続け、かつ健康管理等にかかるコストが少ない方が短期的には利益につながるという考え方があります。しかし奥野さんは、「近年、その考え方が見直されてきている」と話します。社員が心身ともに健やかに働ける環境を整えることこそが、企業の持続的な成長につながる。これが「健康経営」の基本的な考え方なのです。
企業が従業員の健康に積極的に投資することで、社員が元気に働けるようになり、会社全体に活気が生まれます。その活気が、企業が抱える課題に立ち向かう力となり、新しい挑戦への意欲につながっていく。そんな前向きな循環が生まれるのです。
また、従業員の健康に投資することが、優秀な従業員の採用と定着にもつながると奥野さんは語ります。優秀な人の定着は組織の活性化につながり、生産性がアップし、イノベーションの源泉の獲得や拡大、ひいては業績の向上につながっていく。この好循環の最初は「従業員の健康への投資」だという奥野さんの説明には、多くの学生も納得したような反応を示していました。

健康経営に取り組むにあたり、奥野さんたちのチームが最初におこなったのは、同僚など周囲の従業員の声を集めることでした。健康経営推進ワーキンググループを発足させ、立場の違いに関わらず気軽に「ワイワイガヤガヤ」と話し合う「ワイガヤ」を開催するようになったと紹介します。そこではまず「働き方」の課題を発掘するところからスタート。例えば2016年当時、既に都築電気にもあった「テレワーク制度」ですが、当時従業員1300名の会社で使っていたのはわずか13名。聴講している学生たちは高校生時代がコロナ禍ですので、リモートでの授業を経験してきている身からすると、せっかく便利な制度があってもなぜ使われないのか理解しづらいのではないでしょうか。
そんな「ワイガヤ」でたどり着いた答えの一つに「忙しすぎて心の余裕がない人に健康的な働き方をいくら説いても響かない」というものだったと奥野さんは言います。「心の余裕がない人に新しいことを考えることはできない」という言葉には学生たちも思わず頷いてしまいます。そのため、まずは原点に立ち返って、働き方の課題発掘からスタートすることにし、働く環境や残業、テレワークといった身近な話題をテーマに、ワーキンググループで課題のマップ化と施策の一覧化を進めたとのことです。
この課題マップの作成はその当時の働き方を否定するものではなく、なぜそういう状況になってしまっ�ているのか、そしてそれは自分たちが大切にしている価値観とどうつながっているのかを紐解く作業であったと奥野さんは説明します。その大切な価値観を守りながら、次にどうすればよりよい環境にすることができるのかを施策に落とし込んでいき、施策一覧として整えて、経営陣に提案していったそうです。
このような提案を受け、2017年、中期経営計画の3本柱に「健康経営」が位置づけられました。健康経営統括室という部署が設置され、室長には当時の社長自らが就任し、社員全員の前で「健康経営宣言」が発表されたとのこと。これにより、トップダウンと現場の融合が始まり、1ヶ月1本以上の施策の企画と実行を積み重ねて、現在に至る環境を構築できたと奥野さんは説明してくれました。これによりテレワークの例を一つ取っても、970名もの従業員が利用するようになり、残業も少なくなり、大きな成果が生み出されたそうです。
学生は健康経営をどう感じたのか?
ここまで都築電気における健康経営の歴史を紹介したところで、奥野さんから「皆さんはこういった話を聞いてみてどう思ったか、率直な感想を教えてもらえませんか?」との問いかけがありました。これから社会人になっていく若い世代の学生はどのように感じたのでしょうか?数人のグループに分かれて話し合い、そこで出た意見や感想を発表し合います。

まず、最初のグループが思ったことを本音で話してくれました。「私たちが話したのは、先ほど紹介して頂いたワイガヤ制度があっても、仕事が重なってしまっていたり、昼休みの時間に設定されてしまうと参加したくても参加できずに終わってしまうのではないか、という意見が出ました。それを防ぐために上司から参加を推奨してもらえるような制度や雰囲気があると良いのではと感じました」という、学生とは思えない意見がいきなり飛び出しました。
奥野さんは「実際の現場では、参加したいけど、どうしても顧客対応が優先になってしまって参加できないということが起こりがちです。特に取組みをはじめたころは、会社が積極的に参加を促し、参加した社員が不利益を被らないように、環境を整えることがとても重要でした。」との回答がありました。素晴らしい着眼点の発表に教室内が盛り上がります。

続いてのグループからは「都築電気さんの場合は、社長が健康経営をおこなうと宣言して、ワイガヤからいろいろな施策が出て実行することで変革がおこなわれたとお聞きしましたが、働きやすさに課題を抱える企業が健康経営にシフトしていくには、まずはどこから変えていくのが良いと思いますか?」という質問が出ました。
この質問に対し、奥��野さんは「企業の変革には、トップの考え方が大きく影響します。でも、その意識がない場合は、外部の力を借りるのが効果的。まさに『幕末の黒船来航』。外からの刺激が、経営層の意識を動かすきっかけになることもあります。」と答えます。
もうひとつのグループからは「都築電気さんの場合、チームの声が経営陣まで届いたことでいろいろな改革が始まったと思いますが、そういった現場の声を聞かずトップダウンで進む企業風土の会社では、こういったことは難しいのではないかと思いました」と核心を突く感想が発表されました。この感想に対しては奥野さんも思わず唸ってしまいます。
「まさにその通りです。何か新しいことを始めようとすると、必ず反対する人が出てきます。しかも、そういう人ほど声が大きかったりするので、なかなか対応が難しいですよね。ここで参考になるのが、ジェフリー・A・ムーアの『キャズム理論』です。
経営陣の中には、新しいことに前向きな『イノベーター』層もいれば、何を言っても動かない『ラガード』層もいます。だからこそ、まずはイノベーターを早めに見つけて巻き込むことが大事。全員を説得する必要はありません。新しいことに敏感で、応援してくれる人を味方につけて、社内のインフルエンサーになってもらう。すると、その声に共感した『アーリーアダプター』層が集まり、やがて『アーリーマジョリティ』層が動き出します。何かを変えていくには、キーパーソンをしっかりつかまえることがカギと言えるでしょう。」
との回答には質問した学生も納得の表情でした。

最後に「コロナは健康経営にとってどんな影響がありましたか?」という質問も出ました。奥野さんはこの質問に対し「コロナ禍は、健康経営にとっては変革の契機となりました。社会全体で健康への意識が高まり、都築電気でも多様な働き方の普及によって、結果的に従業員の労働時間が減少しました。同時に、睡眠でしっかりと休息が取れている人が多くなりました。人は疲れすぎると、健康的な生活を意識する余裕すらなくなってしまいますが、『しっかり働き、しっかり運動し、しっかり眠る』ことの大切さが、データを通じてはっきりと見えてきました。」と答えてくれました。
学生からの鋭い質問や感想が出たところで前半は終了。後半はもうひとつのテーマである「福利厚生」について、引き続き奥野さんの熱い講義が続きます。
企業の福利厚生と国の社会保障制度を知る
後半は「福利厚生」についての紹介です。学生にとっては少しイメージしづらいかもしれませんが、会社選びではとても重要なポイント。制度があるかどうかだけでなく、使いやすさも含めてしっかりチェックしてほしい――と奥野さんは学生にアドバイスします。

一口に「福利厚生」といっても多岐に渡るため、従業員を支える制度として3つに分けて説明いただきました。
>自律的に生産性高く働くための制度
>福利厚生・健康・お金の制度
>働き続けるためのサポート制度
①自律的に生産性高く働くための制度
多くある制度を細かく奥野さんが紹介してくれます。「ここに当てはまるのはテレワーク、フレックスタイム、資格手当など働く人のモチベーションを高める制度です。テレワークは自分の会社の執務環境以外でリモートアクセス端末を使って勤務することです。仕事をする場所としては、自宅や自宅に準ずる場所(実家など)、会社内に設置されたサテライトオフィス勤務、そして外部のワーキングスペースを使ったモバイルワークです。都築電気ではこれらを自由に使うことができます」
「また、フレックスタイム制度も生産性高く働くためには重要な制度です。必ず勤務しなければならない時間(コアタイム)は決まっていますが、フレキシブルタイムの範囲内であればいつでも出勤・退勤してもよいという制度です。中にはコアタイムの設定のないスーパーフレックスを採用している会社もありますのでチェックしてみましょう」
②福利厚生・健康・お金の制度
2つ目のポイントは、健やかな暮らしをサポートする制度です。
奥野さんが学生に向けて「休暇と休業の違いはわかりますか?」と質問します。さすがに感度の高い学生でも、確かな答えは持っていなさそうな反応です。「休暇とは労働義務のある日に従業員の申請に応じて労働義務を免除することです。有給休暇とか特別休暇のように短期的、スポット的に取得できるもので、目的は従業員の休息やリフレッシュです。一方、休業は従業員が何らかの理由で労働義務を免除される状態を言います。例えば産前産後休業や介護休業などで何らかの理由で就業ができない場合に、会社は労働義務を免除します。法的に決まっているものもありますが、会社によって細部は違ってきますので、内容をよくチェックしたほうが良いでしょう」と教えてくれました。
他にも、様々な学生からはイメージしにくいものの、いざ社会人になってみるとそのありがたみが分かる福利厚生制度について、具体例をもとにわかりやすく解説してくれました。
そして、健康経営の文脈から奥野さんが特に強調したのが「日本は健康に関して多くの支援がある国」という点です。
企業に入社すると加入する健康保険と、加入することで補完される医療費や高額医療費の補助、会社から支給される保障費など、国と企業がきちんと制度を整備している点が紹介されました。
健康経営の第一歩は「定期健診を受けること」だと奥野さんは言います。「病気は年齢に関係なく誰にでも起こり得ます。だからこそ、定期健診はとても大切です。会社に所属していれば、��基本的に無料で受けられるので、若いうちから毎年しっかり受診しましょう。」。
また、学生にはまだ現実感がないかもしれない「自分たちが支払うお金」についても奥野さんが解説してくれます。
「皆さんがお給料をもらうようになると、そこから社会保険料や年金が差し引かれます。きちんと制度を理解して、制度を活用すること、資産を運用することは、一生涯豊かに暮らすため重要なポイントです。心や身体だけでなく、社会的にも健康であるためには、経済的に安定していて、将来に対する不安が少なく、日々の生活に必要なお金を安心して管理できていることも大切だからです」。
③働き続けるためのサポート制度
最後に「働き続けるためのサポート制度」の紹介です。これは、国・企業・民間の協力会社が三位一体となって企業で働く従業員を支えている制度だと奥野さんは紹介します。
ライフイベントに合わせて使える制度の代表格は、育児と介護にかかる制度です。たとえば育児休業や介護休業は法律で定められていて、休業中も雇用保険から給付を受けられるため、社会人生活と育児や介護を両立することができます。
ただ、こうした制度は「知っていないと使えない」のが現実。実際、社会人になってからも制度をよく知らない人は少なくありません。奥野さんは「企業によって制度に違う部分もありますが、ベースとなる国の制度をきちんと理解し、必要なときに使えるようにしておくことが大切」と学生に伝えます。
今回の講義でその存在を知ることができたのは、これか�ら社会に出る学生にとって大きな収穫だったはずです。
最後に奥野さんは、「アンテナ高くもって情報を収集し、自ら学び、実践しましょう。積極的に制度を活用して、自分の人生を豊かにしていってください!」とメッセージを送ってくれました。
学生が感じた国の制度や福利厚生のあり方とは?
最後に、ここまでの話を聞いて感じたことをグループで議論して発表し合います。企業の福利厚生に関して、学生たちはどのように感じたのでしょうか?
ここからは多彩な意見が発表されましたので、奥野さんのコメントとともに一問一答形式で紹介していきたいと思います。

Q:テレワークが減って生産性が悪化したと聞いたが、テレワーク中に仕事に集中できない人もいたのでは?
A(奥野さん): 都築電気では2017年より、従業員アンケート調査にて生産性を測定しています。コロナ前後で生産性は若干悪化していました。ただ、テレワークでも出社でも、仕事への向き合い方には個人差があるので、一つの指標だけで評価せず複合的に分析することが重要です。
Q:制度が多くある中で、社内への認知と使いやすい環境づくりが大切だ��と感じた。
A:今日の講義内容は、普段は新入社員研修で話しているものです。制度を紹介する際は、どこに関心があるかを見ながら、気になる部分を重点的に説明しています。興味を持って最後まで聞いていただき、ありがとうございました。
Q:制度を理解することと、国や企業の情報発信とのギャップを埋めることが重要だと思った。
A:私自身も課長になって初めて知った制度がありました。企業の担当者がすべての制度を都度丁寧に説明してくれるとは限りません。企業の制度は国の制度をベースにしているので、まずは国の制度をしっかり理解してみてください。
Q:現在大学3年生で、就職活動に向けて企業を調べている。企業を見る視点が一つ増えてありがたかった。
A:そう言ってもらえると嬉しいです。就職活動、応援しています!
最後に奥野さんから学生に向けてメッセージが送られました。
「今日のこの時間が、皆さんにとって有意義なものになっていたら嬉しいです。この講義を通じて、皆さんの社会人生活が幸せなものになることを願っています。」
【編集後記】
奥野さんによる90分の講義は、学生にとっても時間を感じさせない密度の高いものであったようです。最後の発表になった「新しい視点を得ること�ができた」というのは、学生同士の会話からは出てこないこの講義だからこそ得られたものであり、長い社会人生活の第一歩をどこからスタートするか選択するという難しい判断を迫られる学生にとって、大きな支えとなっていくのではないでしょうか。
奥野さんの活気溢れる講義は、金曜夕方とは思えない熱気と笑顔に包まれた時間となりました。ブラック企業やパワハラといったネガティブなワードが多く出回り、そしてテレワークを代表とする働き方改革などが叫ばれる中、都築電気の健康経営は、これからの企業のあるべき姿を見せてくれていると感じた90分でした。
引き続き行われた課外授業では、奥野さんの少しプライベートな一面も垣間見ることができました。
話題は人生全般に広がり、和やかな雰囲気の中で会話が続きました。気づけば終電が近づくほど、盛り上がりを見せた時間となりました。

「健康経営」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。
アクサ生命が提唱する『健康経営アクサ式』は、通常の健康経営の範囲である健康管理・健康増進など「心身の健康」だけではなく、「働きやすい環境づくり」や、仕事に対する意義や意味を見出す「働きがい」、さらには、夢や希望など前向きな人生観をもって地域や人との関係を大切にする「生きがい」といった�「トータルな健康」を実現する取り組みです。
この取り組みによって、「企業の永続的な発展と同時に従業員のウェルビーイング(持続的な幸福感)の両立」を目指していきます。
また、私たちの大切なステークホルダーの一員として、これからも「将来世代」のサポートを続けてまいります。
AXA-A2-2508-0571/C0T
法人のお客さまへ
法人のお客さまへ
あなたの会社のさまざまな課題に専門スタッフがお応えし、「100年企業」を目指すためのサポートをいたします。
アクサ生命 公式サイト

アクサ生命 公式サイト
アクサ生命の商品・サービスについてはこちらの公式サイトからご覧ください。